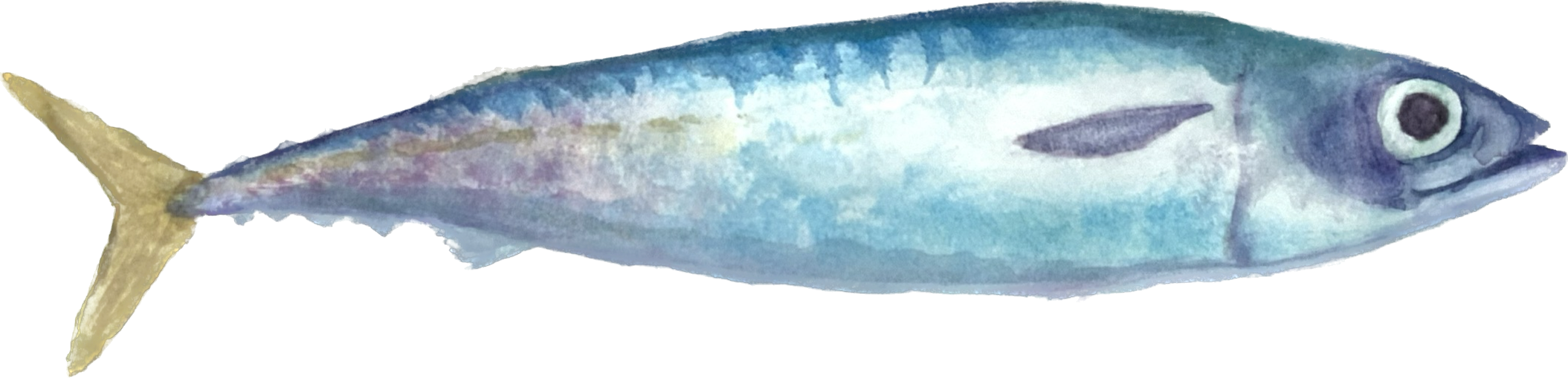大気は、暗鬱な重たい雲と暗鬱な色の海に挟まれて圧縮され、ぼくは特別に濃い冷たい空気を吸っているようだった。風が全然なかった。船も通らない。 やがて、雪になった。はじめのうち、雪片は軽くて、まるで空気の中から次次に湧いて出るように漂っていたが、しばらくすると大きく重くなり、あたり全体を埋めて本格的に降りはじめた。 音もなく限りなく降ってくる雪を見ているうちに、雪が降ってくるのではないことに気付いた。その知覚は一瞬にしてぼくの意識を捉えた。目の前で何かが輝いたように、ぼくははっとした。 どれだけの距離を昇ればどんなところに行き着くのか、雪が空気中にあふれているかぎり昇り続けられるのか、軽い雪の一片ずつに世界を静かに引き上げる機能があるのか。半ば岩になったぼくにはわからなかった。ただ、ゆっくりと、 ひたひたと、世界は昇っていった。海は少しでも余計に昇ればそれだけ多くの雪片を溶かし込めると信じて、上へ上へ背伸びをしていた。ぼくはじっと動かず、ずいぶん長い間それを見ていた。
息苦しかった。
坐りこんで、膝をかかえたまま、雪片が次々に海に吸い込まれて行くのを見ていた。
見えないガラスの糸が空の上から海の底まで何億本も伸びていて、雪は一片ずつその糸を伝って降りて行く。
雪が降るのではない。雪片に満たされた宇宙を、ぼくを乗せたこの世界の方が上へ上へと昇っているのだ。静かに、滑らかに、着実に、世界は上昇を続けていた。ぼくはその世界の真中に置かれた岩に坐っていた。岩が昇り、海の全部が、膨大な量の水のすべてが、波一つ立てずに昇り、それを見るぼくが昇っている。雪はその限りない上昇の指標でしかなかった。