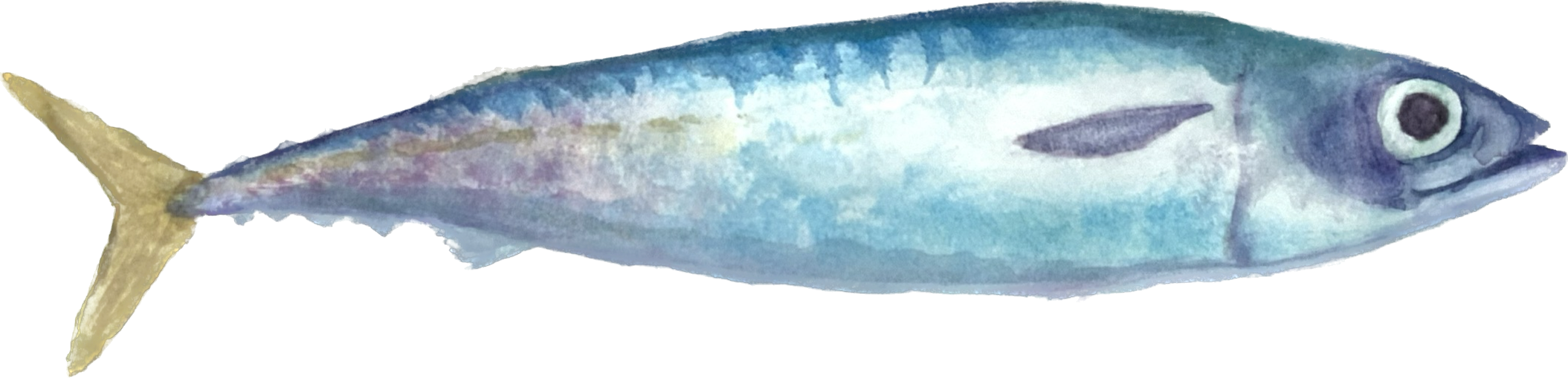しばらく見ているうちに、ハトがひどく単純な生物に見えはじめた。歩行のプログラム、彷徨的な進みかた、障害物に会った時の回避のパターン、食べ物の発見と接近と採餌のルーティーン、最後にその場を放棄して離陸するための食欲の満足度あるいは失望の限界あるいは危険の認知、飛行のプログラム、ホーミング。彼らの毎日はその程度の原理で充分まかなうことができる。そういうことがハトの頭脳の表層にある。
しかし、その下には数千万年分のハト属の経験と履歴が分子レベルで記憶されている。ぼくの目の前にいるハトは、数千万年の延々たる時空を飛ぶ永遠のハトの代表にすぎない。ハトの灰色の輪郭はそのまま透明なタイム・マシンの窓となる。長い長い時の回廊のずっと奥にジュラ紀の青い空がキラキラと輝いて見えた。単純で明快なハトの動きを見ているうちに、ぼくは一種の暖かい陶酔感を覚えはじめた。
今であること、ここであること、ぼくがヒトであり、他のヒトとの連鎖の一点に自分を置いて生きていることなどは意味のない、意識の表面のかすれた模様にすぎなくなり、大事なのはその下のソリッドな部分、個性から物質へと還元された、時を越えて連綿たるゆるぎない存在の部分であるということが、その時、あざやかに見えた。ぼくは数千光年の彼方から、ハトを見ている自分を鳥瞰していた。